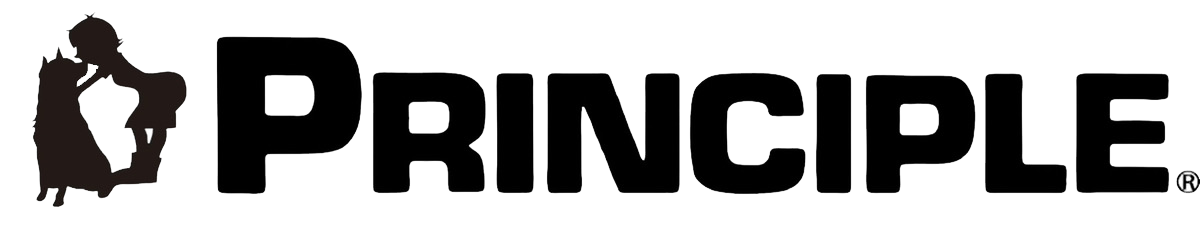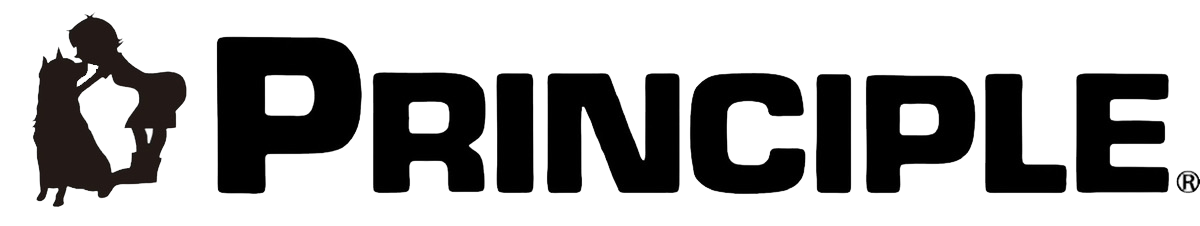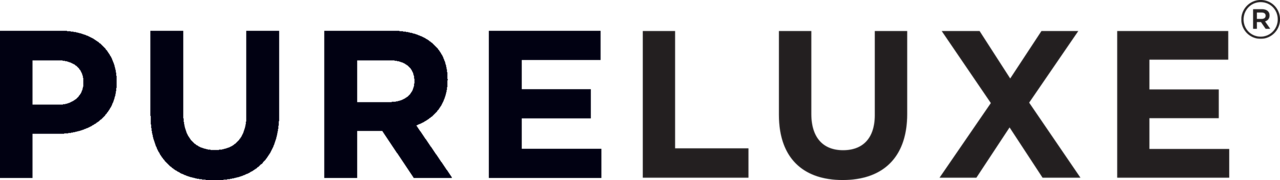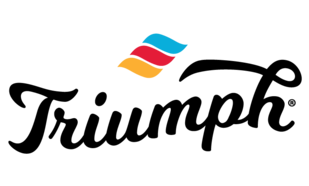原材料の安心・安全なナチュラルドッグフード/キャットフード
営業時間 | 9:00~14:00 月曜日~金曜日(祝日は除く) |
|---|
犬に必要な栄養素(タンパク質・脂肪・炭水化物)
犬に必要な栄養素は、タンパク質・脂肪・炭水化物(3大栄養素)+ビタミン・ミネラル(5大栄養素)
そして、動物が生きるためにとても必要な新鮮な水です。
3大栄養素について
-
タンパク質・・・筋肉・血液・内臓・被毛など体を構成する栄養素
(脂肪や糖質のように蓄えることができないので毎日バランスのとれたドッグフード・良質なタンパク質を与えることが大切です)
ちなみに・・・犬は人の4倍もタンパク質が必要です。
〇欠乏すると・・・発育障害・貧血・病気の回復力低下など
〇過剰摂取すると・・・肝臓・腎臓に悪影響を及ぼします
-
脂肪・・・高カロリーで最大のエネルギー源になります。
(ビタミンA・K・E・Dの脂溶性ビタミン吸収を助ける栄養素)
〇欠乏すると・・・体重・体力の低下
〇過剰摂取すると・・・下痢・肥満など
-
炭水化物・・・繊維質と糖質から構成されていて、脳と筋肉に蓄えられエネルギー源として活用されます。
〇欠乏すると・・・糖質の欠乏は発育障害になります
〇過剰摂取すると・・・肥満などが注意です
犬の健康のためには、研究された高品質な原材料をバランスよく配合しているドッグフードを毎日犬の運動量にあわせて適正量与えることが大切です。
肥満について
ワンちゃんが肥満になると、体のあちこちに支障が現れてきます。
なりやすい病気例
-
関節疾患
体が重くなると、関節に負担がかかりやすくなるものです。遺伝的に関節疾患を持っている(股間接形成不全)場合、肥満になるとさらに悪化する恐れがあります。犬は猫と比べて、遺伝性の関節疾患が多いのが特徴です。
-
心臓病
肥満になると心臓が血液を送るのに負担がかかるため、心臓発作や心不全など、心臓に関する疾患が起こりやすくなります。心臓に過度な負担がかからないように、くれぐれも気をつけましょう。
-
皮膚病
適正体重の頃は大丈夫だったのに、太ったことにより、脇の下やあごなどの皮膚同士が密着する箇所が蒸れてしまうことがあるのです。皮膚が擦れていないか、蒸れていないか、チェックするようにしてください。
-
糖尿病
肥満になると、糖尿病の発生率が高くなります。これは、すい臓から分泌されるインスリンの能力が落ちるために、糖分が体内で活用できなくなるためです。肥満が改善されると、糖尿病の症状が改善されることもあります。
-
肝機能障害
肝臓は、ビタミンやホルモンの合成、栄養分を分解して体内に必要な物質を合成、有害物質を分解するなどしています。肥満によって肝臓に脂肪が蓄積すると過度の負担がかかり、肝機能が低下します。
-
便秘
肥満によって内臓に脂肪が溜まると腸の働きが悪くなるために、便秘になりやすくなってしまいます。
これらの病気にならないために、運動と食事管理を行い、肥満を防ぐようにしましょー♪
愛犬のうんちからわかる健康チェック
ウンチは愛犬の体調を知るバロメーターです。
ふだんから、排泄物や排泄する時の姿勢をチェックしましょう!!
理想的なうんち
適度な水分があり、淡い黄土色から濃い黄土色、形はコロンとしていて、バナナのような
すぐに拾い上げられるものがいいです。
☆うんちのにおいをチェック☆
悪臭がするときは、腸内の異常な分泌物にによるものかもしれないのです。
少しゆるいウンチをした時
発熱や嘔吐などがなければ、ストレスなどによるものなので、様子をみましょう。
長くつづくようでしたら、動物病院でみてもらいましょう。
(子犬や・老犬の場合は一度の下痢でも急激に悪化するのですぐに病院へ)
・水のようなウンチの場合は、細菌やウィルスに感染していることが考えられます。
・血便や真っ黒なウンチの場合、消化器官からの出血が疑われます。
下痢の原因には、ウィルス・ストレス・食あたり・消化できない異物をのみこんだ・有毒な食べ物を飲み込んだ・腫瘍ができた・内臓のトラブルなど いろいろなことが考えられます。
-
ストレスの場合は、ワンちゃんの環境を少し考えて、一緒にいる時間を増やしてあげましょう。
-
湿度の多い季節は、出しっぱなしのフードに気をつけ、いつでも、新鮮な水が飲めるようにしましょう。
新鮮な水を常に飲めるようにしておきましょう。
-
ワンちゃんには、たべてはいけない食べ物(ねぎ・チョコなど)を与えないようにしましょう。
下痢がつづいたり、すっぱいにおいがする、食欲が衰える、血が混じるなどの場合は、すぐに病院へつれていってあげましょう。
愛犬に与えてはいけない食べ物
-
ネギ類 赤血球に対し毒性のあるn・プロピルジスルフィッドという成分が含まれ、 貧血や血色素尿 症などの症状がでることがあります。
注意:ハンバーグ・肉じゃが・たまねぎのスープ・すき焼きなどは熱をあたえても毒性は消えないのであげないようにしましょう。
-
チョコレート、コーヒー テオブロミンが中枢神経と心臓を刺激し、大量に食べると下痢や嘔吐、呼吸困難などを起こす可能性があります。
-
生卵の卵白 アビジンというたんぱく質が、ビタミンB群の一種であるビオチンの吸収を妨げ、 ビタミンバランスを崩す可能性があります。
-
塩分 犬はほとんど汗をかかないので、人間の3分の1程度しか塩分を必要としません。とりすぎると、肝臓などに負担をかけるため、肝臓や心臓の病気にかかりやすくなってしまうこともあります。
-
牛乳・チーズ 下痢を起こす可能性がありますので、与えないようにしましょう。
-
エビ・タコ・イカ・カニ 消化不良や嘔吐の原因になります。
-
鶏の骨 噛み砕いたときに先がとがります。消化できないため、食道や腸などにささって傷つけてしまいます。
-
お菓子やケーキ 肥満の原因です。砂糖は、骨や歯茎を弱めたり、ビタミンCを破壊します。
体型チェック
愛犬の肥満度を日頃からチェックしておきましょう。
-
首:ぽっちゃりしだすと、耳の付け根から首にかけて、脂肪がつきやすくなります。 しわが寄る、首が一回り太くなってきたら要注意
-
のど:アゴから胸にかけてのラインがたるんできたら、脂肪が付いてきたサイン。
犬種や品種によっては首が太いこもいますが、ポチャッとしてくるので、
違いがすぐにわかります。
-
背中・ウエスト:背中からウエストへなだらかなラインが続き、真上から見てくびれているのが 理想です。背中が四角くなっているのは、明らかに肥満体形です。
-
しっぽ:しっぽの付け根は、脂肪が付きにくい箇所でもあるため、ここに脂肪がつくと 肥満度が高い可能性があり。こうなる前に、早めのダイエットが必要です。
-
ろっ骨:肥満予備軍になってくると、胸の部分に厚く脂肪が付くため、
手でさわってもろっ骨を確認することができなくなります。
肥満か、そうでないかをチェックするためにも、さわってみましょー。
※週に1回程度は体を触り、部位の肉付きをチェックして理想的な体系をめざしましょう。
病気のサインを知るためにおしっこチェック
おしっこで一番チェックしてほしいことは、色です。
色が濃い場合・・・水分不足で、脱水症状や発熱の可能性があります。
色が薄い場合・・・水分のとりすぎか、肝臓の機能が低下している場合があります。
赤っぽい場合・・・尿道からの出血が考えられます。
茶褐色の場合・・・尿道にいたるまでの泌尿器科からの出血が考えられます。
(トイレシーツはおしっこの色がわかりやすいもので、毎日色や量をチェックしましょう♪)
おしっこからわかる病気
-
膀胱結石・尿道結石
尿道結石とは、膀胱で作られた結石が、尿道の途中でとまってしまうものです。
時間が経過しますと、尿道に結石がつまって尿がでにくくなるので、排尿時に痛みを伴います。
排尿時にかかる時間が長くなり、回数も増えます。
※できるだけ、水分をとらせるようにする!
※排尿を我慢しないようにさせる!
※下腹部をひやさないようにする!
※外陰部を清潔に保つようにしてあげましょー!
-
腎不全
血液を濾過して老廃物を排出する肝臓機能が低下し、おしっこが無色透明・無臭になります。
※慢性腎不全
進行性の病気のため、できるだけ症状の進行を遅らせる治療をします。
※急性腎不全
腎臓病・尿路結石によって起こることもあります。
尿の量をふやし、余分な窒素化合物を体内から取り除き、
たんぱく質以外の栄養をあたえる治療をします。
-
膀胱炎
細菌感染によるものが多く、他に結石や腫瘍、外傷などによって起こります。
排尿時に痛がることもあり、おしっこに血がまじったり、白く濁ることもあります。
※細菌性の場合は抗生物質の投与を行います。
シニア化のサイン
愛犬の肥満度を日頃からチェックしておきましょう。
顔 (白髪の増加や、目が白濁する白内障は皮膚や目の老化によるもの。耳や口の匂いは、代謝と免疫力の低下や病気の併発も考えられる。)
- 白い毛が増えてきた
- 目が白くにごってきた
- 耳あかがたまりやすい
- 口がくさい
- 歯垢がたまりやすい
体 (同じエネルギーを摂取していても代謝が低下すると太ることがある。一方、痩せてしまうのは消化吸収の機能低下や内臓疾患の可能性も。 )
- 以前より太った(やせた)
- 毛にツヤがなくなった
- 体臭が気になる
- お尻まわりが小さくなった
動作 (腰や足に痛みを感じていたり、視力や聴力が衰えてくる、体力低下など、老化による弊害が動作を妨げることも多くなってくる。)
- 足の動きがぎこちない
- 呼んでもあまり反応しない
- ときどき息切れする
- 物にぶつかるようになった
- 立つ・座るの動作が遅い
気持ち (体の痛みだけでなく、気持ちが乗らない、というのも老化現象のひとつ。いつもの行動ができないこと自体がストレスになることも。)
- ビクビクする(妙に攻撃的になる)
- あまり遊ばなくなった
- 触られるのを嫌がるようになった
- 他の犬(猫)と接触したがらない
食事 (老齢では食の進み方にも変化が出やすい。量より質の食生活が必須。異常にほしがる場合は認知障害かも。)
- フード量が減った(増えた)
- 水もフードも過剰摂取注意。
- ご飯を上手に食べられない
- おやつしか食べない
- 水をたくさん飲む
年をとってきたワンちゃんと楽しみを発見しなおすことでもっと楽しい毎日を送るための4ポイントです。
-
楽しい散歩を演出しよう
散歩は飼い主さんとのコミュニケーションを深め、ストレス解消もできる大事な時間です。
愛犬の性格に合わせ、時にはコースを変えて宝探し的な楽しさをプラスしたり、いつもと同じコースでも、細かいアイコンタクトで安心感をあたえましょう。
-
触ってコミュニケーションをとりましょー
習慣をかえないこと、それが良い作用に働かない場合もあります。
高齢になり不安感を抱えると愛犬には、例えば、ソファーにあがることを解禁したり、リラックスタイムには寄り添うなど、状況に応じ臨機応変さを持って、触れ合う時間を増やしましょう。
-
自信を復活させるためにたくさんほめてあげましょう。
もうトイレもお留守番もできて当たり前になっていて、子犬の頃のように心から褒めることが少なくなっていませんか?いくつになっても、愛犬は褒められることで自分の行動を確認します。いつまでも自信ある行動を促すためには、メリハリあるほめ方をしてあげてください。
-
同じ目線でみてみよう
飼い主さんに従わないのは、たんなるわがままだけということはありません。
何かを伝えたくて一生懸命なのです。
愛犬の行動にはすべて意味があります。
いつも吠える場所や必ず座っている場所などに、愛犬のまねをして寄り添ってみましょう。
その時のしぐさが何を伝えたいか、ヒントがみつかるはずです。
ワクチンについて
子犬の接種時期と回数
生後2ヶ月頃の時期から生後3~4カ月の時期の間に、2回から3回の接種を行います。
※ワクチンの接種によって作られる免疫も一生続くものではありません。接種後も獣医師と十分に相談し、継続してワクチン接種を受けるようにしてください。
ワクチン接種で予防できる病気
-
アデノウイルス1型(犬伝染性肝炎)
アデノウイルス2型感染症
犬アデノウイルスには1型と2型の2種類があります。1型は、子犬の突然死(かかって一晩で死ぬ場合があります)や、発熱、元気がなくなる、食欲がなくなる、嘔吐、下痢、扁桃腺のはれ、目(角膜)が白く濁るといった犬伝染性肝炎の症状をおこします。2型は、肺炎や扁桃腺など呼吸器病を引き起こします。現在2型のワクチンで1型の犬伝染性肝炎も予防できることから、2型ウイルスによるワクチンが主に用いられています。
-
パルボウイルス感染症
パルボ(極小という意味)ウイルスによる急性伝染病で1979年にアメリカで発見され、その後世界中に広まりました。犬パルボウイルスは、チリやほこりに混じって長期生存する、たいへん抵抗性の強いウイルスです。母犬譲りの免疫のない子犬が突然死してしまう心筋型と、激しい下痢や嘔吐を特徴とする腸炎型があります。子犬の場合は、特に症状が重く、死亡率も高いので、注意が必要です。
-
犬パラインフルエンザ
犬パラインフルエンザウイルスは、単独での感染症よりも犬アデノウイルス2型、犬アデノウイルス1型、ボルデテラ、マイコプラズマなどいろいろなウイルスや細菌と混合感染して、気管支炎や肺炎、または一般に「ケンネルコフ」と呼ばれる呼吸器系の疾患をおこすものとして知られています。伝染力が非常に強く、病犬との接触や、咳やくしゃみなどから空気感染を起こすこともあります。気管、気管支、肺に炎症をおこし、激しい咳が特徴です。
-
ジステンパー
ジステンパーウイルスによって感染し、うつりやすく死亡率も高い、犬の代表的な病気です。感染力が強く、死亡率非常に高い病気で、空気感染と、ジステンパーウイルスに感染した病犬から直接うつる場合があります。子犬に発生がもっとも多くみられ、感染すると発熱や食欲がなくなる、膿性の鼻汁、眼やにといった初期の症状から、呼吸器系、消化器系に広がり、激しい咳(呼吸器)や下痢、脱水(消化器)などの症状が現れ、てんかん様発作、後躯麻痺等の神経症状を示し、衰弱死してしまいます。
-
犬コロナウイルス病
犬コロナウイルスによる伝染病で、子犬の場合の症状は嘔吐と中~重度の水様性下痢を引き起こします。潜伏期は1~2日で、軽い胃腸炎の症状の後、多くは回復します。このウイルスは感染した犬の便や尿に放出され経口感染します。
-
レプトスピラ症
レプトスピラ症は、犬だけでなく他の動物や人にも感染の可能性がある伝染病で、細長い螺旋状の細菌であるスピロヘータによって起こります。病原菌は尿中に排泄され、この病犬尿と接触することにより感染します。ネズミの尿も感染源になります。症状には黄疸出血型とカニコーラ型の2タイプがあり、黄疸出血型では、黄疸の他に嘔吐、下痢、歯茎からの出血、血便などがみられます。カニコーラ型は嘔吐、下痢による脱水症状、体温の低下などがあり、手当が遅れると尿毒症を起こし死に至ります。最近はヘブドマディス型を予防できるワクチンも用意されています。
熱中症・熱射病に気を付けましょう!!
暑い日がつづく夏。わんちゃんたちは、夏バテなど大丈夫でしょうか?
犬は寒さには強いのですが、暑さに弱い動物です。
体温調節が苦手なので、飼い主様が十分に注意してあげましょう。
熱射病は環境温度の過上昇により発生します。
この二つは放熱のための呼吸数増加に、肺や心臓の機能が対応できず体温が上昇を続けることによって起こります。
予防策
愛犬をお留守番させるときは、クーラーをつけたり風通しを良くする工夫を!
新鮮な水を常に飲めるようにしておきましょう。
車に乗る時は愛犬を車内に残さないようにしましょう。
夏の散歩や運動は、早朝か夕方以降にしましょう♪
-
肥満犬や短頭犬種(シーズー・ペキニーズ・パグ・ブルドッグ・ボクサー)の場合
熱中症になりやすいので、日頃から肥満にならないように注意しましょう。
もし、かかってしまったら・・・
- 激しいあえぎ呼吸をする
- 大量のよだれが出る
- 体温が40~41℃に上昇して脈拍が速くなる
- 口の粘膜が鮮紅色になる
などの、症状が現れたら、
涼しいところに移動させ、ホースなどで愛犬の体に水をかけ、冷水をたくさん飲ませ、体温を下げることが大切です。
その後、動物病院で診てもらいましょう。
熱中症は重度になりますと死に至ることもあるので、春から夏にかけて注意をして愛犬を見守ってあげましょう。
犬の給餌量
愛犬の毎日食べるごはんの量 愛犬の年齢や運動量によって必要なカロリーが違うので
自分のわんこに必要な量を計算してみましょう♪
計算式:安静時エネルギー必要量(RER)=70×(体重kg)0.75
下の表を参考にして、愛犬の1日に必要な給餌量を計算してみましょう♪
安静時エネルギー必要量(RER)×下のライフステージ=1日に必要なカロリー
(例)160(RER)× 1.8(避妊・去勢未処置の成犬)=288kcal(1日に必要なカロリー・3kgの場合)
表組み見出し
| ライフステージ | DER(kcal/Day) |
| 4カ月までの幼犬 | 3.0× 安静時エネルギー必要量(RER) |
| 4カ月から成犬になる前の幼犬 | 2.0× 安静時エネルギー必要量(RER) |
| 避妊・去勢済みの成犬 | 1.6× 安静時エネルギー必要量(RER) |
| 肥満傾向の成犬 | 1.2~1.4×安静時エネルギー必要量(RER) |
| 使役犬 | 2.0~8.0×安静時エネルギー必要量(RER) |
ここで計算したカロリーをもとに、毎日のご飯の量を調整して、愛犬の便の様子や実際に体を触ってお肉のつき方をチェックしてあげましょう。
犬種によっても、標準体重がありますが個体差もあるので自分の愛犬のベスト体系を保つようにしましょうね。
犬の味覚 こだわり

味の基本感覚は、甘味、酸味、苦味、塩味からの4つに区別されます。
犬の味覚は人と比べると少ないです。
この味覚は、人も犬も舌の表面にあるざらざらした味蕾(みらい)といわれるところで感じとりますが、この味蕾の数によって感覚が変化します。
犬の場合、この味蕾の数が人と比べ低く、人が約9,000あるのに対して、犬は約1,700しかありません。
果物などに含まれる糖や他の甘味物質を感知する能力を持っているので、甘いものを好む場合もありますが、甘味を食べる習慣のない犬は、無関心なようです。
味覚に関する研究では、犬を最初に引きつけるのはドッグフードのニオイですが、
食べ始めるとニオイは全く関係のない存在になってしまいます。
食べている時は、口の中の味蕾と食感受容体にまかされてしまいます。
肉の種類に関する好みは、味よりもニオイによって決定されます。
穀類よりは肉類を好み、味や食感が犬の場合でも大切です。
食の食いつきは、まずはニオイ→食感→味によって判断されるようです。
犬の心臓疾患

心臓強化にタウリン&L-カルニチン♫プリンシプルならバッチリだワン!
犬の心臓疾患の原因
★遺伝子の関与のある場合
僧帽弁閉鎖不全症(心臓弁膜症)
心臓は、左右の心房と心室の4部屋からなりたっています。
血液の流れによって観察すると、全身を還流した静動脈は、前後の大静脈を通って右心房に流出し、右心室の拡張と右心房の収縮によって右心室に運ばれます。
右心室が収縮すると血液は肺動脈に運ばれ、そこで空気中の酸素を血液中に取り入れ、二酸化酸素を血液から放出します。
酸素を充分に取り入れた血液は肺動脈から左心房に運ばれた動脈血は、左心室の拡張と左心房の収縮によって、大動脈に駆出されます。
こうして全身には左心室の収縮によって動脈を通って血液が供給されます。心室の収縮と拡張の繰り返しによって血液が駆出されるわけですが、その際に血液が逆流しないように、心室の入口と出口には弁があります。
僧帽弁の閉鎖は、パラシュートが風を受けて空中で開くのに似ています。僧帽弁自体にはそれを動かす筋肉はありません。左心室が収縮すると血液が風の役割をして便を開き、僧帽弁は閉鎖します。このことにより、左心室の血液は大動脈へ駆出され、手前の左心房へは逆流しないわけです。
僧帽弁は、コラーゲンを含む丈夫な組織ですが、年齢に伴って質・量ともに変化し、弱くなります。弱くなった僧帽弁は、ゴムのように引き伸ばされます。このため、互いに接している弁にすき間が生じ、血液の逆流が起こります。
この状態を僧帽弁閉鎖不全症といいます。
症状
・少し運動すると息切れする
・呼吸困難といった心不全症状
(浅く速い呼吸をし、時に痰を出すようにせき込むこともあります)
・食欲低下
このような症状がみられたら、一度病院を受診してみましょう。
かかりやすい犬種
トイプードル ミニチュアシュナウザー ポメラニアン チワワ コッカ―スパニエル ペキニーズ ボストン・テリア ミニチュア・ピンシャー ウィペット キャバリア・キング・チャールス・スパニエル等
小さい頃から心臓機能を強化しましょう!!
(プリンシプルナチュラルドッグフードは、心臓機能強化のタウリン&L-カルニチン配合ですよ)
★フィラリアのような寄生虫感染による場合
フィラリア症は、フィラリアという寄生虫が感染し、心臓の右心室や肺動脈に寄生することにより起こる心臓疾患です。
予防法
蚊によって媒介されたフィラリアの感染子虫が成長しながら
心臓へ侵入することを阻止することで防げます。
注意
フィラリア予防薬は、正しく使用しない場合、予防効果がえられないばかりか副作用もありますので、獣医師の診察を受けてから処方してもらいましょう♪
はみがき

歯石予防に歯磨きをしましょう♪
◎仔犬のころから口の中をさわれるようにこまめにスキンシップをとりましょう♪
◎歯周ポケットのプラークは、ブラッシングすることで予防できます。
プラークは6~8時間で形成され、歯石は3~5日で形成されます。
注意
ガーゼをまいて指で歯の表面だけをきれいにしていても、歯周ポケットのプラークはとれません。
また、固すぎるひづめなどで歯が折れてしまうこともあるので気をつけましょう。
成犬になってからブラッシングをさせる場合には、少しづつ楽しみながらはじめましょう!
- 1口を開けずに唇をめくるか、さわるだけ。
- 2指に好物の味を付けて歯にさわる。
- 3歯ブラシやぬれたガーゼで少しづつさわる。
- 4ブラッシングしやすい切歯や犬歯から行い、徐々に全体に行う。
- 5口をあけて、歯の裏側(舌側面)をブラッシングする。
1段階づつできたら大げさにほめてご褒美をあげてください!!
※歯周病予防には、食事も関係があり決まった時間に主食を食べ、間食は少なめに。
噛むことで、唾液分泌が促進され、口腔内の汚れが少なくなり、歯周病の予防になります。
粒形状も大きくて硬いもので食べにくい食事の方がよく噛むことができます。
小粒フードは、歯周病予防に適していないようです。
年をとってもきれいな歯でいるためには、毎日のケアがとても大切です。
ごはんを食べたら歯磨きの習慣を身につけましょう。
ワンコの食事がうんちになるまで
食べたものが消化されて便になるまで・・・
口(かむことで食べ物を小さく、唾液を混ぜ合わせて飲み込みやすくします)

食道(飲み込んだ食べ物は食道から胃へ送り込まれます)

胃(胃の動きによって食べ物は胃液と混ざり、ドロドロに溶かされて、十二指腸へ送られます)

十二指腸(十二指腸には、すい臓の導管からすい液が、胆のうから胆汁が流れ込んできて、
食物の消化・分解が進められます)

小腸(小腸の粘膜から分泌される消化酵素で、さらに細かい単位に分解された栄養素は、
小腸で吸収され、血液中に取り込まれます。小腸の内壁には腸繊毛と呼ばれる
突起が多数あり、表面積を増大することで栄養素を効率よく吸収しています)

大腸(小腸で栄養素を吸収された後のものが大腸へ。ここでは水分が吸収され、
最後の残りかすが固まって便になります)

肛門(大腸で作られた便は、直腸を通って肛門から排泄されます)
便のちがい・・・
便の量が増える・・・食物繊維が多くなると便の量は増加します。
便が軟らかい・・・食物繊維は、摂りすぎると腸の蠕動運動が刺激されて、
大腸で水分が再吸収される前に便として排出されるため軟便や下痢に
なります。
色が違う・・・便に色を付けるのは、胆汁の中のビリルビンという物質。
穀類や食物繊維が多いと腸内が酸性になって黄色っぽい色に。
肉が多いと腸内はアルカリ性になって濃い茶褐色の便になります。
カルシウムを摂りすぎると白っぽく固い便になり、
クロロフィル配合のガムやサプリメントで便が緑色になります。
緑色の便・・・胆汁に含まれビリルビンが腸内環境などによって酸化した色で、
小腸や大腸の働きが不十分で、腸で胆汁が再吸収されずそのまま
排出されると緑色の便になります。
強く匂う・・・穀類の消化が苦手な犬は、穀類の多い食事だと消化不良を起こして
便が臭くなることがあります。また、動物性たんぱく質を与えすぎると、
小腸で消化・吸収しきれず、未消化物が大腸まできて、
便を臭くする原因になります。